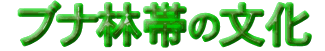
Culture in Beech Woodland

Photo:Gensaku Izumiya 新緑のブナ林
ブナ林の見直しを
世界史を繙くまでもなく、古代文明の発祥地はエジプトやメソポタミアといった乾燥地帯であるが、現代においては、先進国と言われている国の多くが北半球の冷温帯、すなわちブナ林帯に属している。これは、人間の精神活動と肉体活動に適する気候条件を、他の地域より満たしているからであろうと推測されている。
FAO(国連食糧農業機関)の呼びかけによって「国際森林年」となった1985年6月、秋田市で「ブナ林シンポジウム」が開催された。これを契機としてその後、ブナ林に対する再評価の動きが高まった。森林の景観・生態系破壊、災害防止、地球温暖化防止、野生動物保護、水源涵養林・魚付き林としての機能など、さまざまな視点からブナ林の価値が見直された。そして、このような考えに基づいてさまざまな保護運動や市民運動が展開され、現在も続いている。しかし、こうした森林保護運動においては生態学的側面、環境的側面ばかりでなく、同
時に文化的資産としての森林を考察する視点も忘れてはならないであろう。照葉樹林文化とともに、日本人の精神形成に大きな影響を与えたブナ林帯の文化を、今こそ再考すべき時である。
ブ
ナ
林
帯
の
文
化
ナ
林
帯
の
文
化