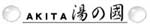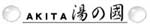日本一の湧出量で知られる玉川温泉の源泉(田沢湖町)
温泉につかったときの開放感や充足感は、一時的なものとはいえ誰もが実感するすばらしい効果である。しかし湯治の効果は、二、三週間続けることにより初めて表れるものだ。実際、こうした7日周期の生体リズムを調節することが治療の根幹であることは、むかしから経験的に知られていた。そして現在では、以下のような温泉療法のメカニズムが、臨床データによって医学的にも実証されている。
[温泉成分の吸収]
温泉の化学成分は、主に皮膚を通して吸収される。いちばん吸収されやすいのは二酸化炭素、硫化水素、放射性物質のラドンといった脂に溶けやすいガス成分である。
次いで、無機成分でも脂に溶けやすい鉄やヨウ素などが吸収されやすく、ナトリウム、カルシウム、硫酸などのイオンもわずかだが吸収される。ただし、吸収されるといってもそれはごく微量で、毎日のように入浴する温泉地の住民でも、摂取のし過ぎによる副作用などは心配ないそうである。
[温泉成分の作用]
吸収された成分は、皮膚のすぐ下の結合組織に働きかけて血管造成作用や免疫能力を高める。同時に、温熱や水圧による循環器の活発化などとともに自立神経や内分泌系、免疫系などの体のひずみを整え、自然治癒力を引き出す。
皮膚疾患に対しては、温泉成分が直接、肌に作用する場合が多い。また今日、アトピー性皮膚炎などステロイド剤(消炎剤)依存による副作用が取り沙汰されているが、こうしたケースでは酸性泉などの刺激で一時的に患部を悪化させ、それを乗り越えることで本来もっている自然治癒力を引き出す、といった方法もとられている。
[入浴以外による温泉療法]
温泉水に直接触れにくい、ぜんそくや肺気腫といった呼吸器系の疾患には、吸入や噴霧などを行なうことも可能である。また、温泉の泥を使った鉱泥浴や鉱泥湿布も成分を深部まで浸透させる効果がある。さらに、温泉の蒸気を利用する蒸気浴(蒸し風呂)は水圧の影響を受けずに入浴効果が得られるので、心臓疾患に適している。
飲泉療法は、日本では飲用許可が厳しいこともあってあまり普及していないが、温泉成分を直接体内に摂取・吸収できるため、消化器系の疾患には有効である。
温泉の入浴効果は、現代医学の中心である医薬品や手術による治療のように即効性は少ないが、数値で割り切れない複雑な人体にさまざまなかたちで働きかけ、総合的に調整することによって効果を発揮する。また、学問的に体系づけることは難しい部分が多いが、温泉療法は作用も効果もおだやかで、しかも現代社会に多い、ストレスによって引き起こされる慢性疾患に適しており、これからは両者それぞれの特徴を生かしながら補い合って、より治療効果を高めることが大切になるであろう。

|




|