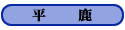 |
 |
| RYOZEKI |
 |
 |
 |
 |
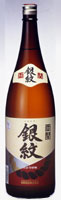
|
| 秋田県南部の湯沢は、かつて佐竹南家の城下町であった。国内有数の銀山として名高い院内が近くにあることから、当時から酒の需要は多かった。しかも、古来より米の産地であったことや水質に恵まれていたこともあって酒造業者の数も多く、その後多くの名酒造家を生み出した。そのひとりが二代伊藤忠吉で、東京滝野川の醸造試験場に出向いて研究を重ね、明治40年に第一回全国清酒品評会で見事一等賞を受賞し、大正2年の第四回では優等賞を受賞した。また、独自の工夫によって、寒冷地に適した低温長期醸造を開発したが、これは現在、県内のほとんどの蔵元で行なわれている方法である。 その後、いち早く全国展開を開始し、県内屈指の蔵元に成長したが、なかでも注目されるのは幻の米「亀の尾」を用いた酒つくりであろう。関西以西では初めて、酒造好適米として認知させることとなり、東北の酒造家に影響を与えた。 現在、大吟醸、吟醸、純米、本醸造、山廃など、製造する酒の種類も多く、全国に出荷されている。なお、平成4年には級別廃止に向けてCIを導入するなど、新たな経営理念に基づいたイメージつくりに取り組んだが、時代の流れや社会環境に対応しながら、消費者の視点にたった酒質を追求する積極性が端的に表れているといえよう。伝統ある古い器に、新しい酒を盛るといった理念は、まさに創業以来の伝統でもある。 |
 |  |
| 吹き抜けになった蒸かし場 | しぼりの作業を行なう「舟場」 |
 |  |
| もろみに櫂入れをする蔵人 | 格調ある建物正面 |
|
[社名]両関酒造株式会社 |
